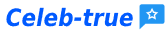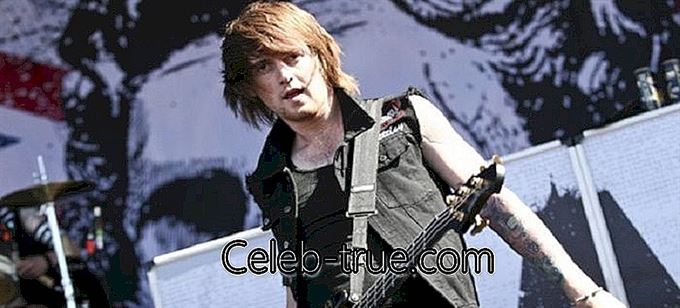ナガルジュナは仏教の哲学者であり、「大乗」仏教の哲学と実践の「マダーヤマカ」の伝統の創始者と考えられています。彼はまた、「ムラーマディヤマカカリカ」と呼ばれるマディヤマカ派の基礎テキストを作成しました。多くの歴史的発見は、ナガルジュナが大乗仏教の中心概念である「プラナパラミタ」の設立に貢献したと考えています。彼は仏教の「スンヤタ」の概念を明確にし、それは英語で「空虚」または「虚無」に翻訳される。 「スンヤタ」の教義は、複数の複雑な意味を提供し、魅力的です。ナガルジュナと彼の弟子アリヤデヴァは、最も重要な仏教の教義のいくつかを構成しているため、最も影響力のある仏教哲学者であると考えられています。彼の人気作品は、彼が「スラバカ」哲学と「大乗」伝統に与えた影響の強力な証拠を提供します。彼は仏の元の哲学を復活させ、偉大な賢者の「マディヤマカ」の教義に新しい視点を与えました。これは、自己inと自己mort責の中間的な方法です。
幼年期および幼少期
ナガルジュナの存在のタイムラインに関する多くの矛盾する文書があります。彼は西暦150年、インド南部、アジアのどこかで生まれたと考えられています。
彼はおそらくバラモン一家に生まれ、サタバハナ国王ヤジナ・スリ・サタカルニに顧問として仕えていました。
ナガルジュナは、アンドラプラデーシュ州グントゥール地区の歴史的都市であるナガルジュナコンダで人生のかなりの期間を過ごしたという複数の主張があります。しかし、ナガルジュナとナガルジュナコンダを結ぶ考古学的な発見はありませんでした。この都市は中世から存在すると考えられており、考古学調査で見つかった碑文は、その時代に「ヴィジャヤプリ」と名付けられたことを示しています。
文学作品
ナガルジュナは、彼の最大の作品である「ムラマダヤマカカリカ」の功績が認められています。「ムラマダヤマカカリカ」は、仏教の中道の基本的な詩から成り立っています。基礎テキストのコレクションは、大乗哲学のマディヤマカ派に基づいています。彼はチベットや東アジアの他の地域で仏教を広める上で最も影響力があると考えられているこのテキストで仏教を復活させました。
「Mulamadhyamakakarika」のテキストはサンスクリット語で書かれており、27の章、12の初期の章、15の後続の章が含まれています。 Nagarjunaは、「Mulamadhyamakakarika」の仏教テキスト「Abhidharma」からのすべての反Madhyamakaの告発の主張に反論した。テキストの節は、人間が経験するすべての現象が、彼ら自身の意識の投影に他ならないことを説明しています。
いくつかの歴史家は、ナガルジュナによって行われた作品について議論しており、彼によって仏教について作られたいくつかのサンスクリットの論文に関する対立があります。 「Sunyatasaptati」、「Vaidalyaprakaraṇa」、「BodhisaṃbharaSastra」、「Sutrasamuccaya」、「Bodhicittavivaraṇa」、「Pratityasamutpadahrdayakarika」などの重要な論文は、彼によって作曲されたと見なされます。
ベルギーのエティエンヌ・ポール・マリー・ラモット教授と仏教の僧inイン・シュンは、論文「Mahaprajnaparamitaupadesa」について意見の相違がありました。 Yin Shunはナガルジュナを示す南インド人によって作曲されたと信じていましたが、ラモットはこれはSarvastivada学校に属する誰かの作品であると主張しました。 Nagarjunaの教育の具体的な証拠はないため、NagarjunaがSarvastivadaの学者であったと信じることは間違いありません。
Nagarjunaは、「Bhavasamkranti」、「Dharmadhatustava」、「Salistambakarikas」、「Mahayanavimsika」、「Ekaslokasastra」、および「Isvarakartrtvanirakrtih」に関する論文や論評を作成したことでも知られています。彼はまた、大乗仏教の経典「ダシャブミカストラ」について解説を書いたと考えられています。
哲学作品
ナガルジュナは、大乗経典を擁護するいくつかの詩と解説を書きました。彼はブッダがマディヤマカシステムを設立したことを認め、彼の中間的なアイデアを復活させました。 Nagarjunaは「Nyaya Sutras」に関する論文を作成し、詩の1つでプラマナの理論を批判しました。
ナガルジュナは「スンヤタ」の概念を強調し、「プラティティアサムパッダ」と「アナトマン」という2つの教義を結び付けました。 「Sunyata」の分析では、「Mulamadhyamakakarika」の「svabhava」を評価しました。彼の「スンヤタ」の評価は、しばしば反基盤主義と見なされています。
複数の学者や歴史家は、ナガルジュナが実際にスンヤタの教義を発明したかどうかを主張しています。一般的な信念は、彼は教義を改革したがそれを発明しなかったということです。
「二つの真実」の教義は、様々な仏教学校で異なって説明されています。大乗仏教のマディヤマカ派で、ナガルジュナは教義を「サティヤ」(真理)の2つのレベルとして説明しました。驚異的な世界では、キャラクターは現実的でも非現実的でもないと考えられています。すべてのキャラクターは不確定であると認められており、本質が空になっています。
ナガルジュナは、マディヤマカの立場を真実の2つのレベルで説明し、現実は2つのレベルに分かれていると述べました。 2つのレベルは、絶対レベルと相対レベルと呼ばれます。この教義に基づいて、「大乗マハパリンニルヴァーナ経」はまた、2つの真理教義と空虚(スンヤタ)以外の本質的な真理についても語っています。
「svabhava」の概念を使用して、ナガルジュナは相対性理論の説明をしていました。相対性理論の説明の中で、ナガルジュナは、長さが短いか長いかに関係なく、対照的な性質の他の物に依存すると述べた。
ナガルジュナはまた、2つの真実の教義を用いて「因果関係」を説明しました。 「原因と効果」の教義の起源を説明して、彼は究極の真実と従来の真実の両方が空であると結論付けました。彼の評価では、原因は、効果のあるイベントを作成できるイベントに他なりません。
レガシー
ナガルジュナは西暦250年まで住んでいたと考えられています。彼は仏教僧院「ナランダ」の長を短期間務めました。彼は、偉大な賢者ブッダの後、仏教の歴史の中で最も批判的な思想家とみなされています。
「ムラマディヤマカカリカ」の研究が続くにつれて、ナガルジュナの哲学は研究に大きな関心を集めました。彼の見解は、彼をニヒリストとして見た西洋人の心には影響しませんでしたが、ナガルジュナの哲学は、より大きな質量に感銘を与えました。彼は今までに生きた中で最も洗練された哲学者の一人とみなされており、彼の見解は永遠です。
速い事実
生まれ:150
国籍:インド人
有名:哲学者インド人男性
年齢で死亡:100
出身国:インド
生まれ:アーンドラ・プラデーシュ
として有名:哲学者